12年前の本なのですが、改めて読む機会があったので。ジャネット・マルカムの『ジャーナリストと殺人者 』について少し。
』について少し。
1970年のこと。米ノースカロライナ州のある町で、母親と娘2人(5歳と2歳)の3人が惨殺されるという事件が発生します(母親は妊娠中だったため、事実上4人の殺人に当たるとも)。父親のジェフリー・マクドナルドは陸軍基地に勤める軍医で、犯人の襲撃にあって気を失ったのですが、切り傷程度の負傷で難を逃れました。それが不審に思われたためか、彼は殺人罪で軍事裁判にかけられます。しかし結果は無罪でした。
ところがその年の秋、マクドナルドはテレビ番組に出演し、そこで陸軍の捜査当局をあざけるような態度を取ります。これが彼にとって誤算の始まりでした。視聴者はマクドナルドの態度に疑問を感じるようになり(普段はハンサムで人当たりの良い人物だっただけに、身勝手な振る舞いが余計に違和感を与えたという面も)、さらに殺された母親の家族が司法省に働きかけた結果、捜査のやり直しが決定。先の無罪判決が出てから9年後に、検察から殺人罪で告発されることとなります。そして1979年8月、7週間続いた陪審裁判の結果、下された判決は「有罪」。マクドナルドには終身刑が科せられました。
実はこの判決が下る前に、再び裁判を受けることとなったマクドナルドは、自分の主張を世に知らしめなければという焦りからか、ジョー・マギニスというノンフィクション作家に「弁護側の視点からこの一件について本を書かないか」という誘いを行っていました。マギニスはニクソン元大統領の選挙キャンペーンに同行し、その内幕を描いた『大統領売り込み作戦』(The Selling of the President)という作品で名前が売れた人物。しかしその後はヒット作に恵まれず、経済的理由もあってこの誘いに乗ることを決めます。彼は有罪判決が出た後も取材を続け、4年後の1983年9月、『フェイタル・ビジョン』(Fatal Vision)という作品を発表します。
マギニスはマクドナルドの弁護団の一員となり、4年に渡る取材中、マクドナルド本人や関係者と親密な関係を築いていました。ところが発表された『フェイタル・ビジョン』は、マクドナルドが犯人であるという立場を取り、彼を異常な性格を持つ犯罪者として描くという内容。マギニスはマクドナルドの無罪を信じているという態度で彼に接しながら、本の原稿は決して見せようとせず、マクドナルドの信頼を裏切るような形で『フェイタル・ビジョン』を出版したのです。内容を一切教えられていなかったマクドナルドは、前宣伝のためにテレビ番組のインタビューに応じ、そこで初めて同書が自分にとって不利な内容であることを知るという仕打ちまで受けています。
ちなみに『フェイタル・ビジョン』ですが、その後の1984年に、映像化までされています:
長い前フリでしたが、いよいよここからが本題。1984年、マクドナルドはマギニスを相手取り、「欺瞞的行為と契約違反」を理由とした損害買収請求の訴えを起こします。3年後の1987年8月、この訴えはマギニス側の実質敗訴で和解に至るのですが、実はこの際、今度はマギニス側が様々なジャーナリストたちに対し、取材を求める提案を行っていました。その誘いに乗ったのがジャネット・マルカムで、彼女がマギニスとマクドナルドを含む大勢の関係者に対して取材を行い、整理したのが本書『ジャーナリストと殺人者』というわけです。
ジャーナリストが情報を引き出すために、取材相手にウソをつくという態度は許されるものなのか。ウソにも程度があって、許されるものと許されないものがあるのなら、その線引きはどこにあるのか。ジャーナリストは取材相手にどう接するべきなのか。逆に取材される側は、取材する側とどのように接し、どのような関係を築くべきなのか。ジャーナリストに不利な記事を書かれるというリスクがあることを知りながら、人間はなぜ、取材されるという行為に喜んで参加してしまうのか――本書の軸はもちろん「マクドナルド対マギニス訴訟」なのですが、それを通じて、様々なテーマが読者の前につきつけられます。
「マギニスの行為は許されるのか」という点については、比較的容易に答えが出るでしょう。本書で紹介されるマギニスの(マクドナルドから情報を引き出すために行った)行為はかなり踏み込んだものであり、取材の早い段階で「マクドナルドが異常な心理を持つ真犯人である」という検察側のシナリオに傾いていながら、マクドナルドに自分は味方であると信じさせるような言動を繰り返しています。原稿を見せるように言われながら、言葉巧みにそれを回避するというのは、マギニス自身も自分の行為が問題となることを理解していた証拠でしょう(取材相手に発表前の原稿を見せるという行為が、倫理的に認められるものかどうかは別にして)。それがどのような法律に違反するかは別にして、読者の多くはマギニスの取材行為に疑問を感じるのではないかと思います。
しかし自分がマギニスの立場だったら、別の行動を取れたでしょうか。経済的に困窮し、この仕事を絶対に成功させなければならない。しかも自分の出世作となった『大統領売り込み作戦』の時と同様に、相手グループの内部に深く潜入しながら取材することができる。そのような状態で、「やっぱり君に不利な内容で書くことにしたよ、それでも取材を続けさせてもらえるかい?」などと正直にお願いするのは難しいでしょう。
さらにマギニスにとって問題だったのは、マクドナルドがいわゆるサイコパスのような、ノンフィクションの題材として「面白い」人物ではなかったという点。取材したそのままを本にしても、きっとベストセラーにはならないだろう、ならばどうにかしてマクドナルドの異常性を強調して書かなければ――そんな思いから、マギニスは必要以上にマクドナルドと親密になり、通常ならば得られないような情報まで集めようとします。また取材した内容をある心理学者に送って、マクドナルドは異常者であるという言葉を引き出します。そうした演出や脚色、あるいは重箱つつきのような行為の結果として生まれたのが『フェイタル・ビジョン』でした。こうした行動はもちろん問題ですが、正直なところ、売れる本をつくるためにあえて過激な内容に描くというのは、作家や編集者にとって抗いがたい行為のはずです。
一方のマクドナルドですが、マギニスの企みに途中で気づき、関係を打ち切ることはできなかったのでしょうか。実際に彼の弁護団の中には、マギニスが深入りすることを快く思わなかった人物も存在します。しかしマクドナルド本人はマギニスをすっかり信じ込んでしまい、普通なら明らかにしないような情報まで彼に渡してしまうのでした。しかし彼が真犯人であったにせよ、そうでなかったにせよ、決着したと思っていた事件で再び裁判を受けなければならなくなった時に、「自分が訴えたいことを親身になって聞いてくれる」相手が傍にいてくれるというのはどんなに嬉しいことでしょうか。しかも相手は、密着取材を通じた作品で名声を得た人物。本書にはマクドナルド以外にも、「ジャーナリストを前にすると、なぜか人は饒舌になる」という話が出てくるのですが、同じ立場に立てば、きっと誰もがマクドナルドと同じような態度を取ってしまうでしょう。相手に自分の話を理解してもらえないかもしれない、自分ではなく検察側の主張を信じてしまうかもしれない、というリスクに目をつぶって。
マギニスにしても、最初からマクドナルドを悪く描いてやろうとしていたわけではありません。検察の描いたストーリーに接したとき、それに説得力を感じ、マクドナルド真犯人説で本を書こうと考えるわけです。そう決意したとき、マクドナルドの周辺には、それを補強するような「事実」が転がっていました。偏執狂的な態度、妻子が惨殺された後なのに捜査当局を嘲笑してしまうような神経、そして不倫関係――マギニスは確かに誇張して物語を描いたのかもしれませんが、彼が見ていたのもまた、真実の一面なのでした。
そう考えると、本書に登場する人々は、誰もが「自分から見た真実」を語っているに過ぎないかのように思えてきます。マクドナルドとマギニス。両者の弁護団と支持者。そしてマクドナルドに有罪判決を下した陪審員や、彼の不倫相手に至るまで、自分がこう信じているということを語るだけで、一向に客観的な真実が見えてきません。しかも本書は筋道立てた理論構成をするでもなく(本文とあとがきに分かれているだけ)、関係者の話と著者・マルカムのコメントがずらずらと続くのですが、彼女はあえてこのようなまとめ方をしたのでしょう。
もちろん本書が扱っているのは、著名なノンフィクション作家とセレブな軍医が争うという、非常に特殊なケースです。しかし同じような関係性、「取材する側とされる側の対立」というのは、程度の差はあれ常にどこかで生まれているものではないでしょうか。特に現代は、Web2.0などという言葉が陳腐なものになっていることからも分かるように、誰もがいつ取材する側に立っても、あるいは取材される側に立ってもおかしくありません。本書に登場する誰かの立場に立たされたときに、自分ならどう行動するだろうか、どのような行動を回避するだろうか、そのためには何に注意する必要があるだろうかと考えることは、誰にとっても有益ではないでしょうか。




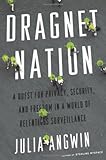



最近のコメント