書店で『本を読むデモクラシー―“読者大衆”の出現 』という本を見つけて読んでいます。「読書の社会史」をテーマに、近代において人々が「本」というメディアとどのように付き合ってきたかを論じた本。その中で、18~19世紀のパリに存在していた「読書室」という商売が紹介されています:
』という本を見つけて読んでいます。「読書の社会史」をテーマに、近代において人々が「本」というメディアとどのように付き合ってきたかを論じた本。その中で、18~19世紀のパリに存在していた「読書室」という商売が紹介されています:
そもそも、本にしても、新聞にしても、まだまだ非常に値段のはる商品だったのである。たとえばバルザックの名作『ゴリオ爺さん』(1835年)は、2巻本で発売されて、その価格は15フランしたというから、現在の感覚でいえば1万円以上した計算になる。これでh、いくら本が読みたいといっても、庶民には、おいそれと手が出るはずもない。
したがって貴族やブルジョワジーは別格として、ふつうの人々は小説や新聞をレンタルで、つまりは「貸本屋」で借りて読んでいたのだ。料金を取って、本や新聞雑誌を読ませる、この商売は、すでに18世紀には、ヨーロッパ各地に存在したという。
ただし貸本屋といっても、店内での読書・閲覧を主としたものだったことから、普通この商売は「読書室」と呼ばれているそうです。これが読めば読むほどネットカフェのイメージ。
要するに、無料の、パブリックな読書空間は、きわめて限られていたのだ。
そこでリシュアンは、毎月の会費10フランを支払って、「ブロス」で、現代文学・新聞・雑誌・詩集などを読みまくり、文壇の動向をキャッチした。真夜中近くまでねばってから、ゆるりと屋根裏部屋にご帰還と相成るのだけれど、「こうすれば、薪もろうそくも使わずにすむ」とあるように、光熱費の節約にもなるから、一石二鳥なのだった。当時の流行作家アルフォンス・カールも、「厳しい季節には、昼食持参の者も多い。実際、1日あたり6スー〔0.3フラン〕で住まいが、机と椅子と、暖房、書物、ペン・紙・インクがわがものになるのだ(『十九世紀の新タブロー・ド・パリ』1835年)と語っている。
「ブログ」というのは「ブロス文芸室」という名の読書室で、リシュアンはバルザックの長編小説『幻滅 』に登場する青年です。また読書室は貧乏学生だけでなく、旅行者にとっても貴重な情報源だったとのこと:
』に登場する青年です。また読書室は貧乏学生だけでなく、旅行者にとっても貴重な情報源だったとのこと:
新聞・雑誌という最先端の情報媒体がそろっている「読書室」は、旅行者たちにとっても大切な場所だった。(中略)異邦人たちや旅行者たちは、どこかの都会に着くと、なによりもまず「読書室」や「カフェ」に足を運んで、最新の情報を入手しようとしたのだ。
で、面白いのは「読書室」において、どのように「本」というコンテンツが消費されていたのかという点。
というのも、読者の熱狂をものすごく駆り立てるものならば、貸本屋は、たくさんの読者の熱意に応えようとして、一巻を三分冊にすることまでも余儀なくされているのだから。その場合、読者は一日単位ではなくて、なんと時間単位で読み賃を払うことになる。
18世紀のパリの様子を紹介した『タブロー・ド・パリ』という本からの引用なのですが、なんと一冊の本を分割して貸し出す(最近の「コンテンツばら売り」の原点!?)ことまで行われていたのですね。また同じく『タブロー・ド・パリ』は、読書室に行けばどんな本が評判になっているか分かることを指摘しています:
きたなくなって、すり切れていても、こうした状態の本こそ、すべてのうちで最良のものであることを物語っているのだ。したがって、むだな意見ばかりいってへとへとになっている批評家は、「貸本屋」に出かけて、人々が求め、借りだして、好んで手にとるような冊子類を実際に確かめてみるべきではないのか。
こうして貸し出し状況や本の状態によって「コンテンツ」の人気が分かるだけでなく、学生が多い読書室などでは、本の内容をめぐってお客同士で議論することもあったようです。現代のネットカフェではお客同士が交流することなどあり得ませんから(あくまでも僕が知っているネットカフェの話なので、最近は違うという話があればご指摘下さい)、コンテンツを軸としたコミュニケーションという点では、18~19世紀の読書室の方が勝っている面があるかもしれません。
"WEB2.0"という流行り言葉(でもなくなってきましたが)を出すまでもなく、いま様々な面でコンテンツの消費のされ方が変化してきていることが論じられています。しかし歴史を見れば、コンテンツが提供者の意図した形で消費されるのではなく、消費者の側がそれを自由に利用するということが普通に行われてきたのかもしれません。変な話、「表紙についた手垢で本の人気が判断できる」なんて、いまのアクセス解析やランキングシステムよりもずっとシンプルで、信頼できるものでしょう。『本を読むデモクラシー』を読んで、過去の事例を学ぶことで現在にも活かせる知識を見つけることができるのかも……と感じた次第です。
![]()





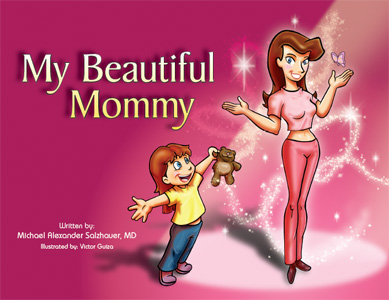

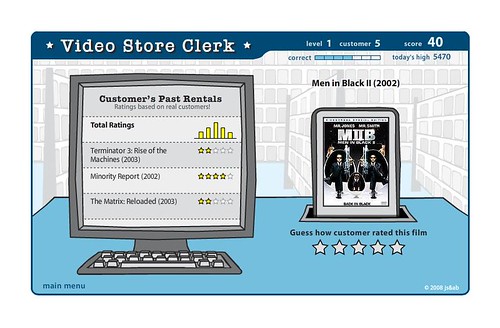
最近のコメント